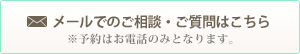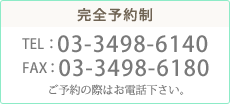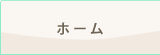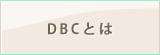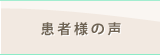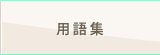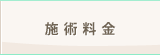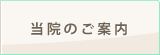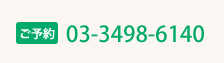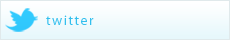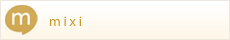用語集
鎮守の森(ちんじゅのもり)
鎮守の森(ちんじゅのもり)とは、日本において、神社に付随して参道や拝所を囲むように設定・維持されている森林の事で、鎮守の杜とも言われます。
古神道における神奈備(かむなび・かんなび)という神が鎮座する森のことで神代・上代(かみしろ)とも言います。
鎮守の森というのは、かつては神社を囲むようにして、必ず存在した森林のことで杜の字をあてることも多い。
「神社」と書いて「もり」と読ませている例もあり、古神道から神社神道が派生したことがうかがえ、また、「社叢」(しゃそう)と称される事も多いです。
神社を遠景から見ると、大抵はこんもりとした森があり、その一端に鳥居がある。
鳥居から森林の内部に向けて参道があり、その行き当たりに境内や本殿があり、その背後には森林の中央部が位置するようになっていて、森の深い方に向かって礼拝をする形になっている。
このことからも「社(やしろ)」が先に在ったのではなく、信仰された森に社が建てられたことが良くわかります。
また海岸近くに魚つき林という、古くから保護された森林がある場合、そこに神社が設けられている例が多いです。
現在の、神社神道(じんじゃしんとう)の神体(しんたい)は本殿や拝殿などの、注連縄の張られた「社」(やしろ)であり、それを囲むものが鎮守の森であると理解されているが、本来の神道の源流である古神道(こしんとう)には、神籬(ひもろぎ)・磐座(いわくら)信仰があり、森林や森林に覆われた土地、山岳(霊峰富士など)・巨石や海や河川(岩礁や滝など特徴的な場所)など自然そのものが信仰の対象になっています。
神社神道の神社も、もともとはこのような神域(しんいき)や、常世(とこよ)と現世(うつしよ)の端境と考えられた、神籬や磐座のある場所に建立されたものがほとんどで、境内に神体としての神木や霊石なども見ることができます。
そして古神道そのままに、奈良県の三輪山を信仰する大神神社のように山そのものが御神体、神霊の依り代とされる神社は今日でも各地に見られ、なかには本殿や拝殿さえ存在しない神社もあり、森林やその丘を神体としているものなどがあり、日本の自然崇拝・精霊崇拝でもある古神道を今に伝えています。